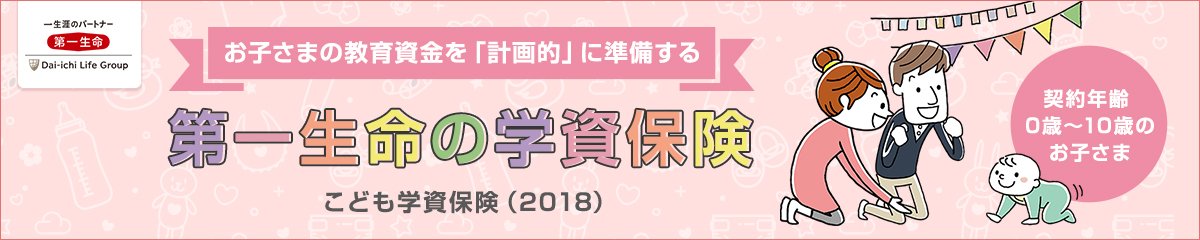学資保険の代わりにNISA?違いやメリット・デメリットを解説


子どもの教育資金を準備する手段として、学資保険のほかにNISAの活用も選択肢として挙げられます。「NISAが本当に学資保険の代わりになるのか」「学資保険とNISAの違いは何か」「どちらが自分に合っているのかを知りたい」などと、興味を持っている人もいるでしょう。
ここでは、学資保険とNISAの違いやそれぞれのメリット・デメリットのほか、それぞれどのような人に向いているのか解説します。
※記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。
※文章表現の都合上、生命保険を「保険」と記載している部分があります。
NISAは学資保険の代わりになる?
NISA(少額投資非課税制度)は、投資により得られた利益が非課税になる、国の税制優遇制度です。
NISAの運用資金はいつでも自由に引き出して使うことができ、その資金を教育費に充てることも可能です。そのため、NISAを学資保険の代わりとして、教育資金の準備のために利用する人もいます。
しかし、学資保険は保険商品、NISAは投資の非課税制度で、資産形成方法が異なります。両方のメリットやデメリットを理解し上手に活用することで、教育資金の確保に役立てられるでしょう。
学資保険とNISAの違い
学資保険とNISAには、どのような違いがあるのでしょうか。表にまとめると以下のようになります。
■学資保険とNISAの違い
横にスライドしてください
|
|
学資保険 |
NISA |
|
確実性 |
契約時に受取額が決まっている |
運用次第で受取額が増減する |
|
収益性 |
受取額が決まっているため、想定よりも収益が増えることはない |
運用次第では大きな収益増が見込めるが、元本割れの可能性もある |
|
現金化 |
途中解約が可能だが、多くの場合で解約返還金は払い込んだ保険料の総額を下回る |
払い出しは自由だが、そのときの運用次第で、投資金額を下回る可能性がある |
|
課税 |
受け取る保険金は原則として課税対象(特別控除額があるため、控除範囲内であれば非課税) |
得られる収益は非課税 |
ここからは、学資保険とNISAの違いについて詳しく解説していきます。
学資保険
学資保険は、子どもの教育費を準備するために加入する「保険商品」です。一定の保険料を払い込むことで、進学時に決まった額の保険金が受け取れます。そのため、資産形成の面では、確実性があるといわれます。受け取れる保険金額が契約時に決まっており、基本的にその金額から増えることはありません。
ただし、満期まで待たずに途中解約すると、解約返還金(解約返戻金)が払い込んだ保険料を大きく下回る可能性があります。
学資保険で受け取る学資金や満期保険金などの保険金は、原則的に課税対象です。保険金を一括で受け取った場合、一時所得として課税されます。なお、受け取った保険金の全額が課税対象にはならず、払込保険料の総額と特別控除額(最高50万円)を差し引いた金額の半分が課税対象となります。
<課税対象となる金額の計算式>
一時所得の金額=受け取った保険金-払込保険料の総額-特別控除額(最高50万円)
課税対象となる金額=一時所得の金額×2分の1
例えば、概算ですが、学資保険の満期保険金が350万円で払込保険料の総額が300万円の場合、特別控除額が最高50万円ですので、実質非課税になります。
NISA
NISAとは、投資で得た利益が非課税になる「少額投資非課税制度」のことです。投資期間は無期限、少額から長期に積立と分散投資が行えます。
NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」という2種類の投資枠があり、それぞれ投資できる商品や運用スタイルが異なります。つみたて投資枠は、長期・積立・分散投資に適した投資信託を対象とし、コツコツと資産形成をしたい人向けの投資枠です。一方、成長投資枠は個別株やETF(上場投資信託)など、より幅広い商品に投資できるため、大きなリターンを狙いたい人向けの投資枠といえます。
特に、つみたて投資枠は金融庁の基準を満たす商品に限定されており、投資初心者でも始めやすいのが特徴です。いつでも自由に引き出せるので、任意の運用期間を定めて積み立てることができます。
投資で得られた利益が非課税になる金額は、年間360万円(つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円)までとなっています。非課税保有期間は無期限ですが、非課税保有限度額は全体で1,800万円(そのうち成長投資枠は1,200万円)までです。
学資保険と比べると、資産の価格変動などにより、投資した資産が元本割れになる可能性があるため、確実性は低いものの、運用次第では収益が見込めるといえるでしょう。また、NISAでは払い出しが自由で、任意の運用期間を定めて積み立てることが可能です。運用益があればその分を教育費に充てられます。
学資保険のメリット・デメリット
契約時に受け取れる金額が決まっており、確実性が高いといわれる学資保険ですが、次のとおりメリットだけでなく、注意しておきたいデメリットもあります。それぞれについて、主なものを解説します。
■学資保険の主なメリットとデメリット
|
メリット |
デメリット |
|
・資金計画を立てやすい ・契約者に万一のことがあった場合、保険料の払込みが免除される商品もある ・生命保険料控除を利用できる |
・インフレリスクがある ・途中解約をすると解約返還金が払込保険料の総額を下回る |
学資保険のメリット
学資保険は、満期に契約時に決めた金額を受け取ることができるため、資金計画を立てやすいというメリットがあります。
また、商品によっては、学資保険の契約者(保険料を負担している人)が死亡するなど、万一のことがあった場合、保険料の払込みが免除されるものもあり、メリットといえるでしょう。その際、保険料の免除だけでなく、契約時に定めた保険金を受け取れる商品もあります。
このほか、学資保険の保険料は生命保険料控除の対象※となり、払い込んだ保険料に応じて所得税や住民税の額を軽減できる点もメリットです。
※所定の要件があります。
学資保険のデメリット
学資保険のデメリットとして、インフレのリスクが挙げられます。インフレとは、物価やサービスの値段が上がり、相対的にお金の価値が下がることです。学資保険は、契約時に定めた金額を将来受け取ることになるため、契約時よりも受取時にインフレが進んでいれば、想定した金額よりも高額な教育資金が必要になり、学資金だけでは不足してしまうという可能性があります。
また、学資保険は、途中で解約するのはデメリットになるといえます。解約返還金を受け取ることができますが、多くの場合、それまでに払い込んだ保険料の総額よりも、受け取れる解約返還金の額が少なくなるからです。
学資保険は、契約時に決められたタイミングや満期を迎える、または途中解約しない限り、現金を受け取ることはできません。自由にお金を引き出せる商品ではないことはデメリットとして理解しておく必要があります。
NISAのメリット・デメリット
NISAにも、次のとおりメリットとデメリットがあります。それぞれについて、詳しく解説します。
■NISAの主なメリットとデメリット
| メリット |
デメリット |
|
・投資で得た利益が非課税 ・インフレリスクに対応できる ・任意のタイミングで引き出すことができる ・家計の収支状況に合わせて投資金額を変更できる |
・元本割れのリスクがある ・投資金額に対する税制優遇措置がない ・商品選びに投資の知識が必要 |
NISAのメリット
NISAのメリットとして、まずは投資で得た利益が非課税であることが挙げられます。通常、株式や投資信託で得た利益(売却益や配当金・分配金)には、約20%の税金がかかりますが、NISAを利用した投資であれば非課税です。
また、インフレリスクに対応できる点もメリットです。NISAの投資対象となる投資信託や株式は日々価格が変動しますが、それらの資産は、インフレに合わせて価格が上昇する傾向があります。インフレにより商品やサービスの値段が上昇することで、企業の業績も上昇し、株価も上昇する可能性があるからです。そのため、NISAはインフレリスクに対応することができるといわれています。
NISAを利用して投資・運用した資産は、任意のタイミングで売却し、現金として引き出すことができます。収益があれば、子どもの教育資金に限らず、ライフイベントで発生するさまざまな出費に対応できるのがメリットです。
NISAでは、投資金額を家計の状況に合わせて変更できるというメリットもあります。ただし、非課税で投資できる金額は年間360万円(つみたて投資枠と成長投資枠を合わせた額)という上限があるため、これを超えないように注意しましょう。
NISAのデメリット
NISAはあくまでも投資であるため、投資した金額が市況に合わせて増減します。つまり、運用次第では元本割れのリスクがある点がデメリットです。NISAで教育資金を準備する場合、必要な時期に必要な金額を準備できない可能性があることにも注意しましょう。なお、長期的に積み立てながら分散投資を行うことで、価格変動リスクを抑えることは可能です。
このほか、NISAでは運用した結果得られる収益は非課税ですが、生命保険料控除のような投資金額そのものに対する税制優遇措置はありません。
また、NISAでは、ある程度の投資の知識が必要な点も、なじみがない人にとってはデメリットといえます。例えばつみたて投資枠の投資対象商品であれば、制度上、金融庁の基準を満たす投資信託が対象となっていますが、それでも選択肢は豊富です。そのため、金融商品を購入する際は、内容やリスクを把握し、自身のリスク許容度の範囲内で資産運用を行うことが大切です。
学資保険とNISA、向いている人とは?
学資保険とNISAは併用がおすすめですが、メリット・デメリットを踏まえて、それぞれどのような人に向いているのでしょうか。学資保険とNISA、それぞれ向いている人を解説します。
学資保険に向いている人
学資保険に向いているのは、次のような人です。
<学資保険に向いている人の特徴>
-
確実に教育資金を用意したい
-
貯蓄が苦手
-
契約者(親権者)に万一のことがあった場合に備えたい
学資保険は受取額が確定しており、リスクを避けて教育資金を準備したい人に向いています。
学資保険の保険料は、契約の際に決定し、定期的に決まったタイミングで定額の保険料を払い込むため、貯蓄が苦手な人でも計画的に教育資金を作ることができます。
また、学資保険の契約者が死亡するなど万一のことがあった場合、それ以降の保険料の払込みが免除され、契約時に定めた保険金を受け取れる商品もあります。生命保険として、万一のときのために備えたい人に向いています。
NISAに向いている人
NISAに向いているのは、次のような人です。
<NISAに向いている人の特徴>
-
投資のリスクを許容できる
-
大きなリターンを期待する
-
教育資金以外の用途でも資金を使えるようにしたい
NISAは運用次第で、投資した金額を大きく上回ることもあれば下回ることもあります。投資は、必要な生活費を除いた、余剰分で行うのがセオリーです。投資のリスクになじみがなかったり、預貯金に余裕がなかったりすると、日々の値動きがストレスになる可能性があります。そのため、ある程度、生活費や貯蓄に余裕があり、一定のリスクを許容できる人にNISAが向いているでしょう。
日々の値動きが反映されるNISAでは、将来的に想定以上に資金が増える可能性があります。リスクを理解したうえで、大きなリターンを期待する人に向いています。
また、NISAは任意のタイミングで自由に引き出すことが可能です。子どもの教育資金に限定せず、幅広い用途に利用できる資金を準備したい人にも向いています。
学資保険とNISAの併用で将来の教育資金に備えよう
学資保険は、あらかじめ受け取ることができる金額が決まっている保険商品のため、投資のように金額が変動するリスクを避け、計画的に教育資金を用意できます。一方でNISAは、投資のリスクはあるものの、子どもの教育資金に限らない用途で利用することが可能です。
そのため「学資保険の代わりにNISA」ではなく、それらを併用するのがおすすめです。学資保険で計画的に教育費を用意しつつ、それ以外の余剰資金でNISAに投資するといった形で、将来の教育資金に備えてみてはいかがでしょうか。
学資保険を検討したいと思ったら、保険会社やFP(ファイナンシャルプランナー)などに、ぜひ相談してみてください。
お得な情報やお知らせなどを配信しています! LINE友だち追加
辻󠄀田 陽子
FPサテライト株式会社所属。税理士事務所、金融機関での経験を経て、「好きなときに好きなことをする」ため房総半島へ移住。移住相談を受けるうちに、それぞれのライフイベントでのお金の不安や悩みがあることを知り、人々がより豊かで自由な人生を送る手助けがしたいと思いFP資格を取得、FPとして活動を始める。現在は地方で移住相談や空き家問題に取り組みながら、FPの目線からやりたいことをやる人々を応援中。
所有資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士、証券外務員一種、日商簿記2級
※この記事は、ほけんの第一歩編集部が上記監修者のもと、制作したものです。
※記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。
※文章表現の都合上、生命保険を「保険」と記載している部分があります。
※税務の取り扱いについては、2024年11月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
(登)C25N0005(2025.4.8)
保険のご相談・お問い合わせ、
資料請求はこちら
お客さまの「一生涯のパートナー」として第一生命が選ばれています。
皆さまの人生に寄り添い、「確かな安心」をお届けいたします。
第一生命では、お客さまのニーズに応じて様々なプランをご用意しております。
月~金 10:00~18:00 土 10:00~17:00
(祝日・年末年始を除く)